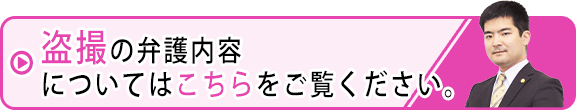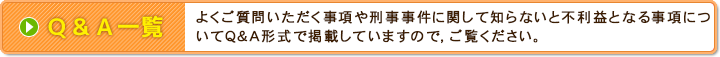「盗撮」に関するお役立ち情報
2023年に刑法改正で新設された「撮影罪」の要件や刑罰などを解説
1 刑法改正で新設された「撮影罪」とは
⑴ 2023年7月13日より施行
性犯罪に関する規定全般を見直す刑法等の改正法案が、2023年6月23日に国会で成立し、同年7月13日より施行されました。
今回の刑法等の改正の中で新設された「撮影罪」は、刑法から独立した「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「法」といいます。)という法律によって定められています。
同法では性的姿態をひそかに撮影する行為のほか、性的な画像の提供・保管・送信・記録などの関連行為も処罰の対象とされています。
⑵ 撮影罪の構成要件
撮影罪(性的姿態等撮影罪)は、以下のいずれかに該当する行為について成立します(法2条)。
①正当な理由がないのに、ひそかに、次(a)(b)に掲げる姿態等(=性的姿態等)を撮影する行為(人が通常衣服を着けている場所において不特定または多数の者の目に触れることを認識しながら、自ら露出しまたは自らわいせつな姿態をとっているものを除く)
(a) 人の性的な部位(性器・肛門もしくはこれらの周辺部、臀部または胸部)または人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち、現に性的な部位を直接もしくは間接に覆っている部分
(b) (a)のほか、わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態
→典型的な「盗撮」に当たる行為です。
ただし、例えば自ら性的な部位を露出しているコスプレイヤーなどを、本人の同意なく撮影する場合などには、撮影罪は成立しません。
②不同意わいせつ罪を構成する行為(暴行・脅迫など)により、同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
→本人の同意を得た対象性的姿態等の撮影でも、その同意が暴行や脅迫などによるもので、本人の自発的な意思によらない場合は、撮影罪が成立します。
③行為の性質が性的なものでないとの誤信をさせ、もしくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、またはそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態を撮影する行為
→例えば「芸術的なヌードだ」と称して性的な利用目的で裸体を撮影する行為や、「自分用」と称してインターネットにアップロードするための性的な写真を撮影する行為も、撮影罪による処罰の対象です。
④正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象としてその性的姿態等を撮影し、または13歳以上16歳未満の者を対象として、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
→13歳未満の者を対象とする性的姿態等の撮影は、本人の自発的なものであるか否かにかかわらず、一律で撮影罪による処罰の対象となります。
また、13歳以上16歳未満の者を対象とする場合も、撮影者が本人より5歳以上年長であれば、本人の自発的なものであるか否かにかかわらず、撮影罪による処罰の対象です。
⑶ 撮影罪に関連する犯罪行為
撮影罪に関連して、以下の犯罪に該当する行為も新たに処罰の対象とされます。
提供等罪(性的影像記録提供等罪)
撮影罪による処罰の対象となっている性的姿態等の複写物(=性的影像記録)を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列する行為について成立します(法3条)。
保管罪(性的影像記録保管罪)
提供等罪に当たる行為をする目的で、性的影像記録を保管する行為について成立します(法4条)。
送信罪(性的姿態等影像記録送信罪)
不特定または多数の者に対して、本人の有効な同意等がないまま性的姿態等の影像を送信する行為について成立します(法5条1項)。
また、送信罪に該当する行為によって送信された影像を、その情を知ってさらに不特定または多数の者へ送信する行為についても、同様に送信罪により処罰されます(同条2項)。
記録罪(性的姿態等影像記録罪)
送信罪に該当する行為によって送信された影像を、その情を知って記録する行為について成立します(法6条)。
⑷ 撮影罪等の法定刑
撮影罪および関連する犯罪の法定刑は、それぞれ以下のとおりです。
【撮影罪】
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
【提供等罪】
① 不特定もしくは多数の者に対する提供、または公然陳列:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金またはその両方
② ①以外の提供:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
【保管罪】
2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
【送信罪】
5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金またはその両方
【記録罪】
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
【日本国民の国外犯も処罰の対象になる】
撮影罪および関連する犯罪については、日本国民による国外犯も処罰の対象とされています(法7条、刑法3条)。
例えば、日本国民が国外において、本人の同意なく性的な映像を撮影した場合は、撮影罪の責任を問われる可能性があります。
2 撮影罪等の新設による変更点:迷惑防止条例との比較
⑴ 変更点
従来は、盗撮行為は主に各都道府県の迷惑防止条例で規制されていました。
しかし、今回の撮影罪等の新設によって、盗撮行為等に関する法規制は以下の各点において大きく変化します。
・盗撮に関する全国一律の法規制の導入
・法定刑の厳罰化
・盗撮された画像・映像の没収が一律可能に
・撮影に関連する行為も刑罰の対象に
⑵ 盗撮に関する全国一律の法規制の導入
迷惑防止条例は、都道府県によって規制内容が異なります。
盗撮行為の規制についても、その要件や法定刑などが都道府県ごとに異なる状況でした。
撮影罪等は法律で定められているため、日本全国において共通して適用されます。
⑶ 法定刑の厳罰化
迷惑防止条例で定められた盗撮行為についての法定刑は、行為の卑劣さに比してそれほど重いものではありませんでした。
今回新設される撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」、不特定または多数の者に対する画像・映像の送信行為(提供等罪・送信罪)については「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金またはその両方」と、盗撮関連行為が厳罰化されています。
⑷ 盗撮された画像・映像の没収が一律可能に
従来の法規制においても、有罪となった盗撮行為によって撮影された画像・映像の記録媒体は、犯罪行為によって生じたものとして没収することができました(刑法19条1項3号)。
しかし、画像・映像のデータそのものや、有罪となった盗撮行為による画像・映像が記録されていない(が、それ以外の盗撮画像が記録されている)媒体は、被疑者・被告人が同意しない限り破棄することができませんでした。
今回の撮影罪等の新設に伴い、従来の法規制では没収・破棄できなかった盗撮画像・映像についても、明文により没収が認められました(法8条)。
⑸ 撮影に関連する行為も刑罰の対象に
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為そのものを処罰の対象とする一方で、盗撮に関連する画像・映像データの提供・保管・送信・記録などの行為は処罰の対象外であるケースが大半でした。
今回の改正では、撮影罪に加えて提供等罪・保管罪・送信罪・記録罪が定められ、盗撮に関連する行為についても広く処罰の対象となります。
これら一連の規定により、盗撮行為自体の抑止に加えて、盗撮された画像・映像データの拡散を防止する効果が期待されます。
3 撮影罪等で逮捕された後の流れ
撮影罪等で逮捕された場合、以下の流れで刑事手続きが進行します。
①逮捕~勾留請求逮捕の期間は最長72時間で、その間に警察官や検察官による取調べが行われます。罪証隠滅や逃亡のおそれを防ぐため、身柄拘束の延長が必要と判断した場合、検察官は裁判官に対して勾留請求を行います。
②起訴前勾留裁判官によって勾留状が発せられると、さらに最長20日間の起訴前勾留が行われます。起訴前勾留期間中も、引き続き警察官や検察官による取調べが行われます。
③起訴・不起訴の判断起訴前勾留期間が満了するまでに、検察官が起訴または不起訴の判断を行います。不起訴であれば刑事手続きは終了ですが、起訴されれば刑事裁判にかけられます。ただし、検察官が100万円以下の罰金を求刑する場合は、被告人が同意すれば略式手続によることも可能です(刑事訴訟法461条)。
④起訴後勾留~公判手続き正式起訴(略式手続きによらない起訴)された場合は、起訴後勾留に移行して引き続き身柄を拘束されます。起訴後勾留期間中は、裁判所に対する保釈請求が可能です。正式起訴からおおむね1か月程度が経過した後、公判手続きが開催されます。公判手続きでは、被告人の有罪・無罪および量刑が審理されます。
⑤判決~刑の執行
公判手続きの審理が熟した段階で、裁判所が判決を言い渡します。控訴・上告の手続きを経て判決が確定し、実刑判決(罰金刑を含む)の場合は刑が執行されます。
当て逃げをしてしまったときの対処と弁護士への依頼 痴漢の刑事弁護