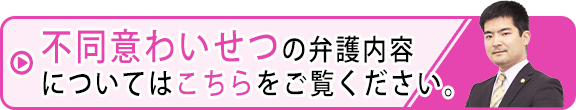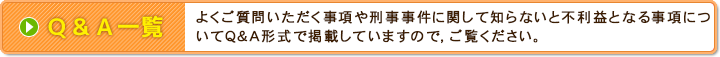「その他性犯罪」に関するお役立ち情報
不同意わいせつ罪で逮捕された場合の不起訴に向けた弁護活動
1 不同意わいせつ罪を犯すとどうなる?
刑法176条の不同意わいせつ罪は、法定刑が6か月以上10年以下の拘禁刑であり、罰金刑のない重罪です。
不同意わいせつ罪で検挙された場合、以下のような流れで事件が進んでいきます。
⑴ 逮捕
不同意わいせつ罪で逮捕されると、警察の留置場に留置され、警察官から取調べを受けます。
警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送ります。
検察官は被疑者を取調べた上、さらに長期間の身体拘束である勾留が必要か否かを判断し、必要と判断すれば、身柄の受取から24時間(かつ逮捕から72時間以内)に裁判官に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に勾留質問を行った上、犯罪の嫌疑の有無、逃亡および罪証隠滅のおそれを吟味して、勾留を認めるか否かを決めます。
※被疑者の家族であっても逮捕されている間は面会できませんが、弁護士はこの間も接見できます。その意味でも、逮捕されたら直ちに刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することをおすすめします。
⑵ 勾留
裁判官が勾留を認めない場合はただちに釈放されますが、勾留が決定されると、勾留請求の日から追加で10日間の身体拘束(勾留)となります。
10日の期間が経過後、さらに捜査の必要性があれば、検察官の延長申請を受けた裁判官の決定で最大10日間の延長が認められます。
このように、勾留は合計最大20日と長期間に及びます。
⑶ 起訴
起訴・不起訴については、勾留期間中に検察官が決定します。
その際には、被害者との示談の成否、前科・前歴の有無、自白・否認、犯行態様の悪質性等、様々な事情が考慮されます。
2 不同意わいせつ事件における弁護士の活動
このように、不同意わいせつ事件を犯すと逮捕され、長期の勾留・起訴に及ぶ可能性があります。
身体拘束が長期化すると、日常生活に大きな影響を与えます。
そこで、不同意わいせつ罪で検挙されたら、一日でも早く弁護士に弁護活動を依頼するべきです。
弁護士は、性犯罪について以下のような弁護活動を行います。
⑴ 逮捕・勾留段階の接見
弁護士は、直ちに被疑者が逮捕されている警察署に出向いて接見し、被害者から詳しく事情を聞き取り、その後の取調べの注意点、手続きの流れを説明して、被疑者の意向も考慮した上で弁護方針の検討を行います。
逮捕段階では、被疑者のご家族は本人に会うことができません。
しかし、弁護士は逮捕段階でも接見が可能です。
ご家族からの伝言などを弁護士が被疑者に取り次ぐこともできますので、被疑者も安心ができるでしょう。
⑵ 釈放に向けた活動
被疑者の学校の無断欠席や、会社の無断欠勤が続くのは、当然避けたいところです。
学校では、単位が取れなかったり退学になったりする可能性があります。
勤務先では、無断欠席を理由に解雇される可能性があるでしょう(そうでなくとも、事件が発覚すれば懲戒解雇となる可能性もあります)。
これらの危機を避けるためにも、早期に釈放されるための弁護活動が非常に重要となります。
弁護士は検察官に対して、家族の身元引受書や上申書、弁護士意見書を提出することで、裁判官へ勾留請求をしないように働きかけます。
また、検察官が勾留請求をした後、裁判官が勾留決定や勾留延長決定をしてしまった場合でも、弁護士は、勾留決定・勾留延長決定の取り消しを求めて「準抗告」という裁判を提起することができます。
準抗告の結果、勾留の要件を満たしてないとの結論に至れば、勾留決定・勾留延長決定が取り消され、被疑者は釈放されます。
⑶ 被害者との示談交渉
不同意わいせつ等の性犯罪の弁護活動において、被害者との示談は極めて重要なものとなります。
示談が成立することで、逮捕・勾留を回避できたり、仮に身体拘束されても早期に釈放されたりする可能性があります。
また、検察官が起訴処分・不起訴処分の判断をする際にも、示談成立は被疑者に有利に働くことが期待できます。
示談交渉を行うには、被害者の連絡先を知る必要性があります。
検察官や警察官は、弁護士に限り、被害者の了解を得た上で、その連絡先を教えてくれます。
すなわち、弁護士がついていなければ、被疑者は被害者の連絡先を知ることはほぼ不可能なのです。
不同意わいせつ行為を受けた被害者の心傷や恐怖は相当のものといえますので、被害者との折衝も含め、示談交渉は刑事弁護のプロである弁護士に委ねるべきといえます。
なお、被害者が未成年(18歳未満)の場合には、親権者である両親が示談交渉の相手方となります。
我が子に不同意わいせつ行為を行った被疑者への怒りは非常に強いことが普通ですから、示談交渉は成年の被害者の場合よりも慎重さが求められます。
⑷ 保釈請求
起訴後は、「保釈」という制度があります。
保釈とは、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを前提として、保釈金を収めることで被告人の身柄が解放され、一時的に社会に復帰できるという制度です(もちろん、公判には出廷しなければなりません)。
保釈に付された条件に違反することなく裁判が終了すれば、保釈金は返還されます。
保釈請求では、弁護士は、裁判官に面接して、被告人が逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないこと、身柄引受人がいて指導監督をすることを主張します。
自白事件で、凶悪事件ではない場合には、裁判官は保釈金の納付と保釈条件の遵守(住居の指定、旅行制限、被害者や証人との接触制限など)を条件として、保釈を認めてくれることが通常です。
⑸ 起訴後の弁護活動
示談が成立しても、悪質な犯罪や再犯の場合などは起訴される可能性があります。
しかし、起訴されてもなお、示談の成立は、執行猶予の獲得や刑期の軽減など、被疑者の今後について非常に重要なものであることに変わりありません。
すなわち、示談が成立すれば、検察庁や裁判所での処分が被疑者にとって軽いものとなる可能性が高まります。
非親告罪となってからも、性犯罪の捜査にあたっては、被害者の意思を尊重する運用がなされていますし、検察官や裁判官は、示談が成立し被害者が許したという事実を被疑者に有利な事情として考慮してくれるからです。
起訴前に示談を断わられていても、示談金の増額によって納得を得られるケース、時間の経過とともに被害感情が落ち着き理解を示してくれるケース、被告人やその家族の度重なる真摯な謝罪が被害者の心を動かすケースなど、起訴後に被害者が対応を考え直してくれる例は珍しくありません。
よって、起訴後であっても、弁護士は諦めずに被害者との示談成立を目指して活動を行います。
どうしても示談に応じていただけない場合には、示談金を法務局に供託したり、贖罪寄付をしたりするという手段もあります。
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら、お早めに刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。